「当事者意識」はよく目(耳)にする言葉ですよね。
筆者としても「何事も“当事者意識を持って”主体的に取り組むのが大事だ」という見解です。
一方で、
仕事や行事などで「当事者意識を持って云々」といったワードが出ると若干の違和感(もやっと感)を感じることはないでしょうか?(それって、やりがい搾取じゃないの?とか。)
この違和感が生じる理由(筆者なりの解釈)は、
- 取り組む/取り組まないのも当事者としての主体的な選択となりうるもの
- 当人(当事者)の問題なのに他人(特に立場の上の人)から期待・要求される点
- とはいえ、やっぱり大事ではあるので、どう向き合うか?
この辺りを整理していくとスッキリできるのではと思います。
ちなみに、
「当事者意識」というこの言葉、よく職場や学校などで聞かされるので、「仕事」や「行事」に対する取り組み姿勢のことだと思っていませんか?
本当は、ライフスタイルや人生そのものにあてはまるかなり深いテーマではないでしょうか。
「自分の人生は、自分が主役」
当事者意識を高めることで、仕事や行事に限らず、「あらゆることは自分が決断していて、その決断の責任も自分が持っている」と感じられるでしょう。
「自分の人生の主権は自分が握っている状態」となり、組織の中での振る舞いはもちろん自分の人生をどのように生きるか(=ライフスタイル)を主体的に選択することができるといえます。
ということで、この記事では「当事者意識」とは何か?を解説し、当事者意識を高めるおすすめの書籍を5冊を紹介します。
- 7つの習慣(スティーブン・R・コヴィー:著)
- 嫌われる勇気/幸せになる勇気(岸見 一郎/古賀 史健:著)
- 限りある時間の使い方(オリバー・バークマン:著)
- 夜と霧(ヴィクトール・E・フランクル:著)
- 自分の中に毒を持て(岡本太郎:著)
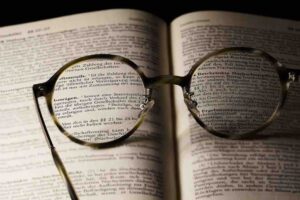
当事者意識とは、結局何なのか?
当事者意識は辞書では次のように定義されています。
「自分自身が、その事柄に直接関係すると分かっていること。関係者であるという自覚。」
goo辞書より引用
「人は誰もが何かに所属している」わけで、家族や学校、地域社会、企業、国、人類、宇宙・・・どんな事柄にでもあてはまることだといえます。(決して、会社や学校の中だけではありません。)
つまり、「自分は、常にあらゆる周囲に(自分自身に対しても)何らかの影響を及ぼしている当事者」であるということです。
「当事者意識」の使い方としては以下のような言い方をします。
- 当事者意識が『ある』
- 当事者意識を『持つ』
- 当事者意識を『高める』
当事者意識は、自覚するだけではなく高めていくことも大事ですね。
❶ 取り組む/取り組まないのも当事者としての主体的な選択となりうるはず
一般的には、以下のような考え方が学校教育の段階から染み付いているような気がします。
当事者意識を持って取り組む=与えられた仕事や課題に対して、前向きに頑張って取り組むこと
でも本来、どのように取り組むかも個人の問題であるはず。
「当事者意識」と「主体性」の違い
物事の関わりを自覚するのが「当事者意識」ですが、自分の意思や判断によって行動する姿勢や能力が「主体性」です。
- 当事者意識:自分自身がその事柄の関係者である、という自覚
- 主体性:自分の意思や判断によって行動する姿勢や能力
もちろん、自分の意思や判断で「取り組まない」というのも主体的な選択の一つになるって訳です。
❷ 当人(当事者)の問題なのに他人(特に立場の上の人)から指示・要求される
あらゆることの当事者であるなら、限られたリソース(時間、労力、お金)をどう配分するかは自分の選択次第。
なのに、学校でも会社でも、そこに所属しているのであれば、その一員として望ましい行動をとってもらいたいと周囲は期待しますよね。
当人の問題を他人が当然のように期待したり、要求したりするのは筋違いでしょう。
「もっと都合よく動いてほしい」と期待するのであれば相手を社畜としてみなしている様なもの。
一方で、チームの中である役割を担っているのに、その役割として期待される行動に至っていない、というケースもあよくあることでしょう。
こういった場合、「当事者意識が足りないんだよなぁ」とか不満を抱いても意味がなく、具体的なアドバイスをしてあげれば良いのかなと思います。(それ以上の意識については相手の問題。)
❸とはいえ、やっぱり大事ではあるので、どう向き合うか?
ここまで説明しておきながら、「自分がやりたくはないことはやらなくても良い」とお伝えしたいわけではありません。これではただの自己中ですよね。
かといって、周囲からの期待や要求に忖度していては自分を犠牲にするだけ。
じゃあ、どうすれば?というと、
シンプルに、
今の自分の立場・状況において、「自分(や自分たち)」のために主体的にどういう姿勢を選択するか?ということに尽きるのではと思います。(決められたこと、与えられたことに対する周囲からの期待とかはもう関係無し)
一方で、場合によっては「やるべきでは無い」という判断もあるでしょうし、「やりたくない」役割を担ってしまうのであれば変える(変えて貰う)ように努力するというのも当事者としての主体的な行動ではないでしょうか。
「何かを指示されたからやっているだけ」という姿勢は周囲に良い影響を与えることはないでしょうし、それ以前に「当人にとっても、その時間が有益なものになりません」よね。
当事者意識を高め、主体的な人生を送る為におすすめの本5選
様々な事象に対し当事者であるという自覚を意識しながら生活を送っていると、次第に、人生そのものについても自分次第だと思えるようになってきます。
そして、自分が影響を及ぼすことができる一番の対象とは「自分自身」ですよね。
自分自身で「選択する」というのは全て自分の責任として実行できる権利です。
- 「もっと忍耐強く(ある)」
- 「もっと賢く(ある)」
- 「もっと愛情深く(ある)」
このように “自分はどうあるか” はどんな環境であれ自分自身で選ぶことができます。
もちろん意識しただけはなく、主体的に行動を起こさなければなりません。
ここからは、主体的な行動につながるきっかけになる本を紹介したいと思います。
- 7つの習慣(スティーブン・R・コヴィー:著)
- 嫌われる勇気/幸せになる勇気(岸見 一郎/古賀 史健:著)
- 限りある時間の使い方(オリバー・バークマン:著)
- 夜と霧(ヴィクトール・E・フランクル:著)
- 自分の中に毒を持て(岡本太郎:著)
おすすめの本❶:7つの習慣(スティーブン・R・コヴィー:著)
何をどうするかというのは、その人それぞれの環境や課題によって異なると思いますが、誰にでも当てはまる普遍的な原理原則というものがあります。
今回記載している内容を踏まえて本当に参考になるのが、この「7つの習慣」という本です。
「当事者として主体的に」といった内容がこの本のタイトルにある7つの習慣の1つめの習慣になります。
ビジネス書としては超有名ですが、ただ名著だからといって読むのと、目的を持って読むのとでは大きな差があります。
おすすめの本❷:嫌われる勇気/幸せになる勇気(岸見 一郎/古賀 史健:著)
「嫌われる勇気」タイトルというから、「他人に嫌われたって良いからやりたいことをやろう」といった内容と勘違いしやすいですが、こちらも自己啓発書としてベストセラー。
人は周囲の人との関係に悩むけれど、それは自分以外の人の課題(あなたの課題ではない)、という「課題の分離」がポイント。
おすすめの本❸:限りある時間の使い方(オリバー・バークマン:著)
物事に対して当事者であるという自覚ができ、主体的になった状態と言えど、何を最優先事項と考えるのでしょうか。
人生における優先事項を決める上で、重要な指標は「有限である時間」です。
今までの過去がどうであれ、これからの未来をどうしたいか?(=目的)を考えてみましょう。
おすすめの本❹:夜と霧(ヴィクトール・E・フランクル:著)
人生の意味とは?それ自体に一般的な答えはありませんし、人生は思い通りなるというわけでもありません。
しかし、あなたの人生というのは、あなたがどう振る舞うかによって決まるのであり、まず問われるべきなのはあなた自身の姿勢なのだ。
というのが、この本の主旨。
ちなみに、邦題の「夜と霧」ではどんな内容か分かりにくいですが、英語版は “Man’s Search for Meaning” で、訳せば「人間が生きる意味を求めて」です。
下記は第2次世界大戦中にナチス・ドイツによって強制収容された経験から独自の心理学理論を提唱したヴィクトール・フランクルの著書「夜と霧」からの有名な一説。
あらゆるものを奪われた人間に残されたたった一つのもの、それは与えられた運命に対して自分の態度を選ぶ自由、自分のあり方を決める自由である。
「夜と霧」(ヴィクトール・フランクル著)より引用
おすすめの本❺:自分の中に毒を持て(岡本太郎:著)
なんだかんだと回りくどく説明しているのですが、もっと直接的にガツンと脳みそを揺さぶられる刺激が欲しい方は、「自分の中に毒を持て」を最初に手に取って貰えればと思います。
まとめ
今回は「当事者意識」について解説し、おすすめの本を5冊紹介しました。
- 7つの習慣(スティーブン・R・コヴィー:著)
- 嫌われる勇気/幸せになる勇気(岸見 一郎/古賀 史健:著)
- 限りある時間の使い方(オリバー・バークマン:著)
- 夜と霧(ヴィクトール・E・フランクル:著)
- 自分の中に毒を持て(岡本太郎:著)
あらためて
「自分の人生は、自分が主役」
です。
当事者意識を磨き、主体的に行動していくことで人生は好転していくものかと思います。








